人気メーカーの家庭用蓄電池を
適正な価格安心施工最大15年保証
全てセットにしてご提案します
※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。







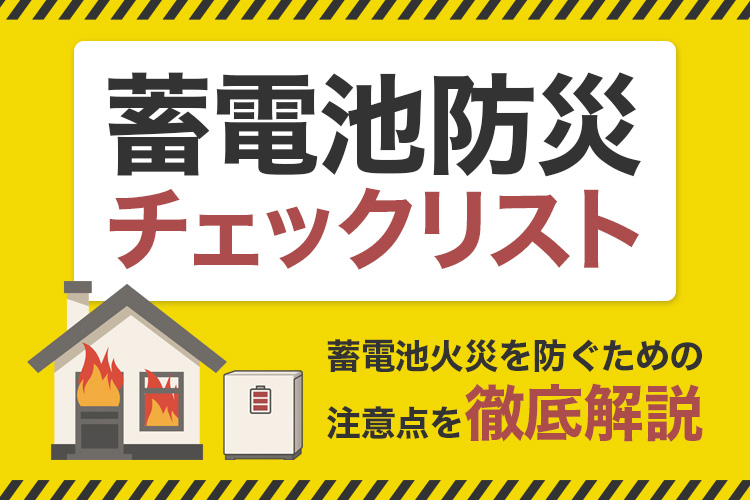

蓄電池の導入が進む一方で、「火災リスク」への不安を感じていませんか?
実際に起きた事故例や、見落とされがちな設置ミス、日常のちょっとした不注意からでも火災が発生することがあります。
本記事では、火災の原因から具体的な予防チェックリスト、万が一の対応方法、保険の使い方まで、ユーザー目線で徹底解説します。
この記事を読めば、火災リスクを最小限に抑えるための実践的な知識が身につきます。それでは早速、火災を防ぐための具体的なポイントを見ていきましょう。

関連記事:【2025年】家庭用蓄電池のおすすめ製品とメーカーを紹介!価格・性能を徹底比較

近年、蓄電池を原因とする火災事故が国内外で頻発しています。
特にリチウムイオン電池を使用した製品において、充電中や使用中に発火するケースが報告されています。
2024年6月、韓国京畿道の電池工場で火災が発生し、23人が死亡しました。
この工場には約3万5千個の電池が保管されており、火災はわずか数十秒で広範囲に拡大しました。
また、2024年5月にはアメリカ・カリフォルニア州の大型蓄電池施設で火災が発生し、14日間にわたり燃え続けました。
この火災では有毒ガスが発生し、周辺住民約1500人が避難を余儀なくされました。
日本国内でも、電動自転車やモバイルバッテリーの発火事故が報告されています。
これらの事故は、製品の品質管理や使用方法の問題が原因とされています。
蓄電池火災は、単なる物的損害にとどまらず、人的被害や環境への影響も深刻です。
特にリチウムイオン電池の火災では、高温や有毒ガスの発生により、消火活動が困難になります。
| 被害・影響 | 具体例 |
|---|---|
| 人的被害 | 火傷、煙による窒息、死亡事故 |
| 物的損害 | 建物の全焼、機器の破損 |
| 環境汚染 | 有毒ガスの放出、水質・土壌汚染 |
| 経済的損失 | 操業停止、補償費用の発生 |
これらの被害を最小限に抑えるためには、蓄電池の正しい取り扱いや定期的な点検が不可欠です。
また、万が一の火災に備えた適切な防火対策も重要となります。

リチウムイオン電池は高エネルギー密度を持ち、軽量であるため多くの電子機器に使用されています。しかし、その構造上の特性から発火リスクが存在します。
電池内部には可燃性の電解液が含まれており、内部短絡や外部からの衝撃、過充電などにより熱暴走が発生する可能性があります。
熱暴走が起こると、電池が急激に加熱され、発火や爆発に至ることがあります。
特に、電池の劣化や製造上の欠陥がある場合、発火リスクが高まるため、適切な取り扱いと保管が重要です。

蓄電池の設置や施工において、適切な手順が守られていない場合、火災の原因となることがあります。
例えば、配線の接続ミスや絶縁不良、適切でない設置場所の選定などが挙げられます。
これらの施工不良は、電気的なトラブルを引き起こし、発火に繋がる可能性があります。
また、定期的なメンテナンスが行われていない場合、劣化した部品や蓄電池の異常を見逃すことになり、火災リスクが増大します。

蓄電池は使用環境の影響を受けやすく、特に温度や湿度の管理が重要です。
高温多湿な環境では、電池内部の化学反応が活発になり、劣化が進行しやすくなります。
また、直射日光が当たる場所や通気性の悪い場所に設置すると、蓄電池の温度が上昇し、発火のリスクが高まります。
| 環境要因 | リスク | 対策 |
|---|---|---|
| 高温 | 熱暴走による発火 | 通気性の良い場所に設置し、直射日光を避ける |
| 高湿度 | 内部腐食や絶縁不良 | 湿度管理を行い、防湿対策を施す |
| 埃や塵 | 通気口の詰まりや放熱不良 | 定期的な清掃とフィルターの設置 |
これらの環境要因を適切に管理することで、蓄電池の安全性を高め、火災リスクを低減することが可能です。


家庭用蓄電池は、災害対策や電気代の抑制に役立ちます。一方で、誤った使い方や設置ミスによる火災も報告されています。
以下は、家庭用蓄電池で起こりやすいトラブルと対策です。
| トラブル内容 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 発火・爆発 | 内部ショート、過充電、衝撃 | 安全基準を満たした製品の使用と定期点検 |
| 膨張・変形 | 長期使用や高温環境 | 室温の維持と異常時の使用中止 |
| 異常発熱 | 経年劣化や内部不具合 | メーカー推奨の点検頻度を守る |
これらのリスクは、導入前の確認と導入後の管理で大きく軽減できます。
産業用の大規模蓄電池は、トラブル時の被害も広範囲に及びます。発電所や企業の運用に影響するため、管理体制の強化が不可欠です。
近年発生した重大事故として、2024年に鹿児島県のメガソーラー施設で起きた蓄電池火災があります。
この事故では、蓄電池の爆発により消防隊員が負傷し、施設の一部が全焼しました。
高温多湿な場所や直射日光が当たる環境は避ける必要があります。空調や換気も重要なポイントです。
機器の劣化や異常は、定期点検により早期に発見できます。点検は必ず専門業者に依頼することが望ましいです。
火災発生時に備えて、通報体制や避難マニュアルを整備しておくことが重要です。従業員への定期的な訓練も効果的です。
産業用蓄電池は管理項目が多いため、導入時から専門家のサポートを受けることが推奨されます。
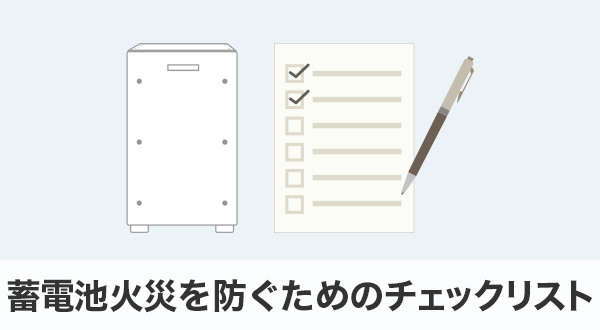

蓄電池の安全な運用には、信頼できる設置業者の選定が不可欠です。
以下の5つのポイントを確認することで、適切な業者を見極めることができます。
| チェック項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 施工実績 | 過去の施工事例や実績を確認し、経験豊富な業者を選びましょう。 |
| 資格保有 | 電気工事士などの資格を持つ技術者が在籍しているか確認してください。 |
| 保証内容 | 機器や工事に対する保証が明確に提示されているかを確認しましょう。 |
| アフターサービス | 設置後の点検やトラブル対応など、サポート体制が整っているか確認してください。 |
| 見積もりの明確さ | 費用の内訳が詳細に記載されており、不明瞭な項目がないか確認しましょう。 |
蓄電池を安全に使用するためには、機器の型番や製造元、PSEマークの有無を確認することが重要です。
PSEマークは、電気用品安全法に基づき、製品が安全基準を満たしていることを示すマークです。
リチウムイオン蓄電池は特定電気用品に該当し、ひし形のPSEマークが表示されている必要があります。
購入前に、製品本体や取扱説明書にPSEマークが表示されているかを確認しましょう。
また、製造元や輸入事業者の情報も併せて確認することで、信頼性の高い製品を選ぶことができます。

蓄電池の設置環境は、安全性に直結する重要な要素です。適切な環境での設置と法令の順守が、火災リスクを低減します。
| 環境要因 | 推奨対策 |
|---|---|
| 温度管理 | 直射日光を避け、通気性の良い場所に設置しましょう。 |
| 湿度管理 | 湿度が高すぎる場所は避け、防湿対策を講じてください。 |
| 防水対策 | 屋外設置の場合は、防水性能のある筐体を選び、適切な防水処理を施しましょう。 |
| 法令順守 | 電気用品安全法や建築基準法など、関連法規を遵守した設置を行ってください。 |
これらの対策を講じることで、蓄電池の安全性を高め、火災リスクを最小限に抑えることができます。
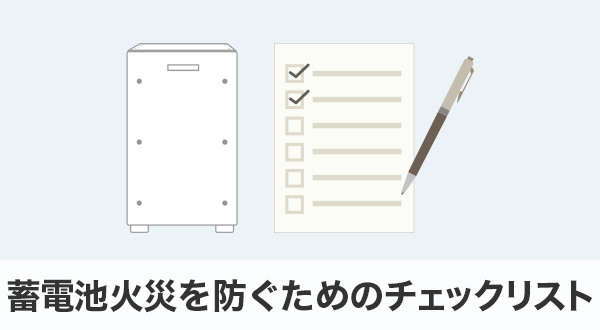
蓄電池の安全な運用には、日常的な観察が欠かせません。
異常音や発熱、異臭などの兆候を早期に発見することで、重大なトラブルを未然に防ぐことができます。
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 異常音 | 通常と異なる音が発生していないか確認します。 |
| 発熱 | 本体が異常に熱くなっていないか手で触れて確認します。 |
| 異臭 | 焦げ臭いにおいや化学薬品のようなにおいがしないか確認します。 |
| 外観 | 膨張や変形、液漏れなどの異常がないか目視で確認します。 |
これらの異常を発見した場合は、直ちに使用を中止し、専門業者に連絡してください。

蓄電池の安全性を維持するためには、定期的な点検が重要です。
点検の頻度や内容は、蓄電池の種類や使用状況によって異なりますが、一般的な目安を以下に示します。
| 点検項目 | 推奨頻度 | 点検内容 |
|---|---|---|
| 外観点検 | 月1回 | 腐食、膨張、液漏れの有無を目視で確認します。 |
| 電圧・電流測定 | 年1回 | 蓄電池の電圧や電流値を測定し、異常がないか確認します。 |
| 絶縁抵抗測定 | 年1回 | 絶縁状態を測定し、漏電の有無を確認します。 |
| 充放電試験 | 2年に1回 | 蓄電池の充放電性能を確認し、劣化状況を把握します。 |
| 保護装置の動作確認 | 年1回 | 過電流保護装置や遮断器の動作を確認します。 |
これらの点検は、専門の技術者による実施が望ましいです。
また、点検結果は記録として残し、異常があった場合は速やかに対応しましょう。

近年、多くの蓄電池システムには、スマートフォンやパソコンから状態を確認できるモニタリング機能が搭載されています。
これらの機能を活用することで、異常の早期発見や効率的な運用が可能になります。
| 機能 | 活用方法 |
|---|---|
| リアルタイム監視 | 蓄電池の充放電状況や残量をリアルタイムで確認できます。 |
| 異常アラート | 異常が発生した場合、アプリを通じて通知を受け取ることができます。 |
| 遠隔操作 | 外出先から蓄電池の設定変更や運転モードの切り替えが可能です。 |
| 履歴データの確認 | 過去の運転データを確認し、運用状況の分析が行えます。 |
これらの機能を活用することで、蓄電池の状態を常に把握し、異常があった場合には迅速な対応が可能となります。
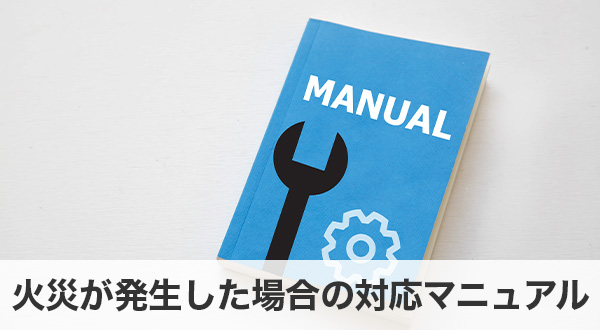
蓄電池火災は急速に拡大する可能性があるため、迅速かつ冷静な初期対応が求められます。以下の手順に従って行動しましょう。
火災が拡大している場合や消火が困難な場合は、無理に消火を試みず、速やかに避難してください。

蓄電池火災に対する適切な消火方法と、避けるべき行動を理解しておくことが重要です。
| 消火方法 | 注意点 |
|---|---|
| 消火器の使用 | 電気火災に対応した消火器を使用します。 |
| 大量の水での消火 | 少量の水では逆効果になる可能性があるため、大量の水を使用します。 |
| 濡れた布で覆う | 小規模な火災の場合、濡れた布で火元を覆い、酸素を遮断します。 |
避けるべき行動として、以下の点に注意してください。
これらの行動は、火災の拡大や二次災害を引き起こす可能性があります。
火災が発生した場合、再発防止のために詳細な記録と報告が必要です。以下の項目を記録し、関係機関へ報告しましょう。
| 記録項目 | 内容 |
|---|---|
| 発生日時 | 火災が発生した正確な日時を記録します。 |
| 発生場所 | 建物内のどの場所で発生したかを明確にします。 |
| 火災の状況 | 火災の規模、煙や炎の状態、異常音の有無などを記録します。 |
| 使用機器の情報 | 蓄電池の型番、製造元、設置年月日などを記録します。 |
| 対応状況 | 初期対応の内容、通報時刻、避難状況などを記録します。 |
これらの情報は、消防署や保険会社、製造元への報告に必要となります。また、再発防止策の検討や改善にも役立ちます。

蓄電池の安全性確保のため、法規制や規格の整備が進められています。
2023年5月31日、総務省消防庁は蓄電池設備に関する省令等を改正・公布しました。主な改正点は以下のとおりです。
| 蓄電池容量 | 消防法令への適合 | 消防機関への届出 |
|---|---|---|
| 10kWh以下 | 対象外 | 不要 |
| 10kWh超~20kWh以下 | 消防法令への適合またはJIS規格への適合 | 不要 |
| 20kWh超 | 消防法令への適合 | 必要 |
JIS規格では、蓄電池の安全性に関する要件が定められています。
例えば、JIS C 4412では低圧蓄電システムの安全要求事項が規定されており、JIS C 8715-2では産業用リチウム二次電池の安全性が定められています。
これらの規格に適合することで、消防法上の外部延焼防止措置と同等の安全性が確保されるとされています。

蓄電池が火災などの被害を受けた場合、適切な保険に加入していれば損害を補償することが可能です。
主な保険とその特徴は以下のとおりです。
| 保険の種類 | 補償内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 火災保険 | 火災、落雷、風災、雪災などによる損害を補償 | 地震や津波による損害は対象外 |
| 動産総合保険 | 火災、落雷、水害、事故などによる損害を補償 | 地震や津波、ユーザーの過失による損害は対象外 |
| 自然災害補償 | メーカーや販売店が提供する自然災害による損害を補償 | 火災保険が適用される場合は、そちらが優先される |
地震による損害に対しては、地震保険への加入が必要です。
ただし、地震保険では蓄電池などの設備が補償対象外となる場合があるため、事前に保険会社に確認することが重要です。
また、蓄電池の設置後に保険の補償対象となるかどうかを確認し、必要に応じて保険内容の見直しを行いましょう。

蓄電池を選ぶ際には、安全性と信頼性を重視することが重要です。
| 選定ポイント | 具体的な内容 |
|---|---|
| 安全認証の取得 | JIS規格やPSEマークなどの安全認証を取得しているか確認します。 |
| 製品の実績 | 過去の導入実績やユーザーの評価を参考にします。 |
| 保証内容 | 長期保証やアフターサービスの充実度を確認します。 |
| 技術力 | 最新の技術を取り入れているか、製品の性能を比較します。 |
これらのポイントを総合的に評価し、自宅のニーズに合った蓄電池を選びましょう。

蓄電池の導入を検討する際には、専門家の意見を取り入れることで、より適切な選択が可能になります。
| 専門家 | 相談内容 |
|---|---|
| 電気工事士 | 設置場所の選定や配線計画など、技術的なアドバイスを受けます。 |
| エネルギーコンサルタント | 家庭の電力使用状況を分析し、最適な蓄電池の容量やタイプを提案してもらいます。 |
| 販売業者 | 製品の特徴や価格、補助金の情報などを提供してもらいます。 |
| 自治体の窓口 | 地域の補助金制度や設置に関する規制について確認します。 |
これらの専門家と連携することで、蓄電池の導入をスムーズに進めることができます。

蓄電池は便利な設備である一方で、火災のリスクも伴います。そのリスクを最小限に抑えるためには、事前の備えが欠かせません。
本記事で紹介したチェックリストは、その第一歩として役立ちます。施工前の確認から日常点検までを習慣化することで、事故の予防につながります。
特に異常音や発熱、においといった初期兆候は見逃さないことが重要です。日頃から注意を払い、小さな変化にも気付ける環境を整えておきましょう。
火災対策は一度確認して終わりではなく、継続的な管理が必要です。機器の劣化や環境の変化にも対応できるよう、定期点検の体制を整えましょう。
また、正しい知識を持つことで、万が一の際にも冷静に対応できます。初期消火の判断や通報手順、消火器の種類まで把握しておくと安心です。
保険や法令についても理解を深めておくと、万が一の損害に備えられます。
リスクを正しく捉え、必要な準備を行うことが、自分と家族を守ることにつながります。
安全な蓄電池ライフを実現するために、今できる備えから始めてみてください。
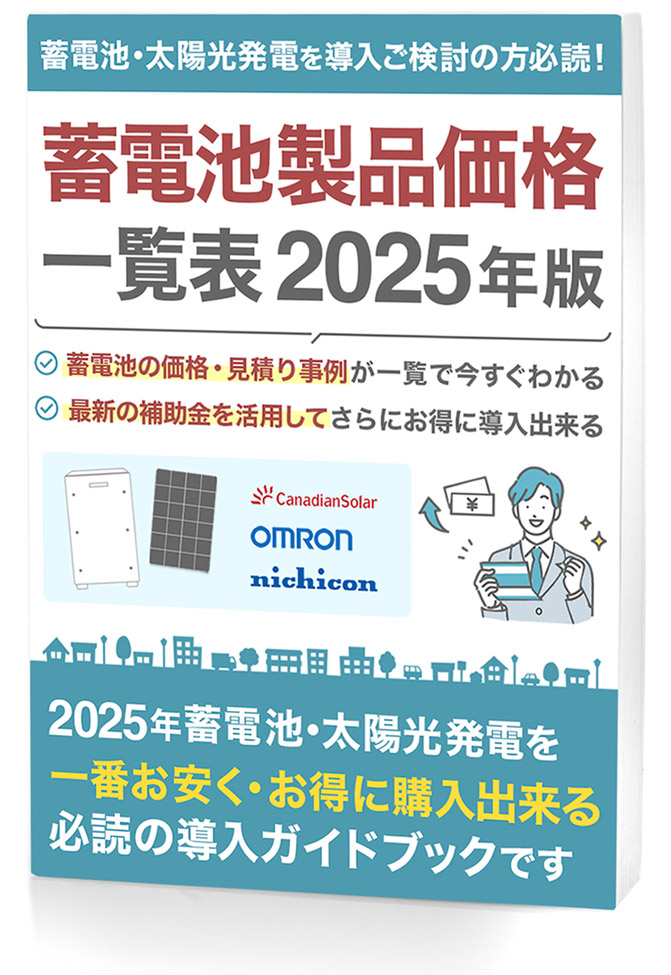
\ 公式LINE友だち登録で /
蓄電池価格表を無料ダウンロードする



※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。







蓄電池
太陽光発電
V2H